『ストロベリーナイト』(光文社文庫)100万部突破!さらに「姫川玲子シリーズ」累計300万部突破!
著者は作品世界に対してすべての決定権を持っている。 それはその通りですが、玲子や菊田、勝俣といったお馴染みの面々との 距離感は、意外と読者の方と変わらないのではと、私は思っています。 100万部は大変嬉しい到達点ですが、同時に通過点でもあります。 私自身、今後の玲子たちの活躍に期待し、楽しみにしています。 また一緒に、玲子に会いにいきましょう。 誉田哲也
誉田哲也氏ロングインタビュー
警察小説以外にも、青春小説やホラーなど、多彩なジャンルで作品を発表し続ける誉田哲也さんだが、「姫川玲子」は特別なミューズ(女神)だと語る。シリーズに込めた思いや映像化にまつわるエピソード、初めて公にされるシリーズの今後の展開など、気になる核心を聞いた。
聞き手 友清 哲さん

- ストロベリーナイト
2008年9月9日発売
定価:667円+税

- ソウルケイジ
2009年10月8日発売
定価:686円+税
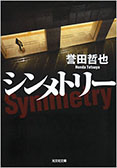
- シンメトリー
2011年2月9日発売
定価:590円+税

- インビジブルレイン
2012年7月12日発売
定価:743円+税

- 感染遊戯
2013年11月8日発売
定価:640円+税

- ブルーマーダー
2015年6月11日発売
定価:740円+税
ミリオン突破は「わかりやすい到達点」
――『ストロベリーナイト』100万部突破、おめでとうございます。これにあわせて、姫川玲子シリーズ累計では300万部突破となりました。まずは率直なご感想からお聞かせください。
誉田:本当に嬉しいことですし、ありがたいですね。これまでにもシリーズ累計で100万部、200万部といった節目はあったわけですけど、ひとつの作品単体でのミリオンというのは僕にとって初めてで、非常に大きな区切りだと感じています。それに、“ミリオン突破”というのは到達点としてわかりやすくていいですよ。他人から「『ストロベリーナイト』ってどのくらい売れてるんですか?」と聞かれた時、「ミリオンいきました」と言えるわけですから(笑)。
――誉田さんはよく、「玲子は自分にとってミューズ(女神)」と表現されていますが、まだまだそのミューズの力は衰えそうもありませんね。
誉田:そうですね。そもそも僕に初めて「重版」というものを味わわせてくれたのがこの作品ですし、テレビでの映像化も『ストロベリーナイト』のスペシャルドラマが初。また、そうしたメディアミックスの効果で作品の売れ行きが一気に上がるような経験も、すべて玲子が与えてくれたものです。作家デビューして、“いつかこうなったらいいな”と夢想していたことを、次々と体験させてくれました。
――とりわけ今年は、『ストロベリーナイト』の映画化などもあり、シリーズにますますの勢いがついた年でもあったと思います。作品やご自身を取り巻く環境に、何か変化は感じていますか?
誉田:たとえばこれまでだったら、ファンの方から『ストロベリーナイト』を「読みましたよ!」と声をかけていただくところを、今年は「観ましたよ!」と言われることが多かったですね。それは本来、監督やプロデューサーにかけてあげてほしい言葉ですけど(笑)、映画やドラマをきっかけに原作を手にしてくれる方もたくさんいるので、やっぱり嬉しいことです。
――その映画版『ストロベリーナイト』ですが、こちらも非常に大きな反響を呼びました。
誉田:竹内結子さんや西島秀俊さん、武田鉄矢さんなど錚々たる演者の皆さんが、ドラマにも映画にも毎回そろって出演してくださって、なんというか、キャストの皆さんそれぞれがキャラクターを育ててくれているようにすら感じています。これは原作者冥利に尽きますね。
――こうして個性豊かなキャストによって映像化され、キャラクターに新たなイメージが加わることは、原作の執筆に何か影響を与えていますか?
誉田:映像のイメージにキャラクターの描写が引っ張られるようなことが、まったくないわけではありません。ただ、映像のなかで表現された部分を、わざわざ否定するような描き方をすることはないですね。むしろ、映像のほうでつくっていただいたイメージが参考になることだってありますから、いい意味でのコラボレーション効果が生まれていると思います。
――それは主要キャラでたとえると、どのような部分でしょう?
誉田:たとえば小出恵介さんが演じてくれた葉山などは、僕が最初に書いた時とはまったくイメージが異なっているんです。でも、小出さんが震えるようにして演じてくれた葉山の姿には、ある種のリアリティを感じました。もともと葉山に関する描写は少なかったので、ああいう“解釈”をもって演じていただいたことがヒントとなり、今後は原作でも違った面が出てくるかもしれないですね。逆に、玲子などは竹内結子さんよりもっと長身の設定なんですけど、まさか急に背を縮めるわけにもいきませんから、さりげなく身長を具体的に数字で書くような描写は控えてみたり……(笑)。
――いまではすっかりはまり役の西島秀俊さん(菊田)も、当初はファンから「イケメンすぎる!」と、ギャップに戸惑う声も挙がっていました。多くの読者はそれまで、菊田という人物をもう少し無骨なイメージでとらえていたように思います。
誉田:それは國奥先生(監察医)のせいでもあるんですよ。彼が菊田を「ゴリ男」なんて呼んだりするから、必要以上にそういうイメージが強まっているんですけど、実際には國奥先生が言うほどゴリラっぽい顔だとは、僕ももともと思っていないです。あれは単なる、國奥先生の嫉妬です(笑)。
姫川玲子シリーズの面白さを分析する
――さて、実に多くの読者を虜にしてきた姫川玲子シリーズですが、その隠れた醍醐味のひとつとして、リアリティが最大限に担保されている点が見逃せません。たとえば警察機構内の人事異動ひとつをとっても、決してご都合主義に陥らない配慮がされていますが、こうした誓約が創作上の“枷”になることはありませんか?
誉田:それはむしろ逆で、制約のなかで書く楽しさというのがあるんですよ。これはスポーツなどと同じで、ルールの範囲のなかでどのような作戦を立てるか、という部分を僕は楽しんでいます。もし何でもありのルールになれば、試合はめちゃくちゃな展開になってしまい、成立しませんよね。
――誉田作品では、さらにそこに「テーマ性」と「娯楽性」という、不可欠の二大要素が加わります。
誉田:そうですね。ただ、それによって創作が苦しくなることはありません。いくつもの制約が存在することで、ある程度やれることの“幅”が定まってきますから、その範疇のなかでいかにエンターテインメントを成立させるかが腕の見せ所。逆に、何を書いてもいいと言われたら、僕自身が書いていて面白くないでしょうね。
――また、物語内の時間軸に沿って、登場人物がちゃんと年齢を重ねているのも、このシリーズの特徴ですね。
誉田:たとえば『ストロベリーナイト』と『ソウルケイジ』では、ほんの数カ月のあいだに起こった事件を描いています。しかし、すべての事件をこのペースで描いていくと、物語のなかでの時間が経過しない分、今度は舞台の状況に変化が乏しくなってしまう懸念があります。
――その場合、具体的にはどのような問題が発生するのでしょう?
誉田:仮に、このあと玲子を本部に復帰させようと思った場合。警察という組織の性質上、ああいう経緯を経て本部復帰を目指すには、ある程度の期間が必要になります。それでもフィクションだからいいやと異動を強行すると、リアリティが損なわれてしまいます。僕としてはこれはやりたくないわけです。
――ここでもやはり、人知れずリアリティの担保に苦心されていることが窺えます。
誉田:僕はそういった点を無視して物語を描くことができないタチなので。もちろん、そうした本来必要な時間をすっ飛ばすための“理由”を考えることは可能ですけど、それは1枚かぎりのジョーカーのようなもの。つまり、そう簡単に切っていいカードではないということですよ。
――誉田さんは「ドルチェ」シリーズをはじめ、他にもミステリーの枠組みを複数持っています。発想したひとつの事件は、どのような基準で割り振っているのですか?
誉田:猟奇的な事件や凄惨な事件だったら、少なくとも「ドルチェ」には向きませんから、玲子シリーズ、もしくはノンジャンルの作品として構成することになります。性質的にマッチしそうな事件を思いついたら、玲子に第一選択権があるんです。まず玲子に「こういうネタあるけどどう? やってみる?」とお伺いを立ててみて、彼女が興味を示さないのであれば、他のシリーズにまわすという(笑)。
――すっかり“誉田一座”のチーフ格、といったイメージですね。
誉田:そう。だからあまりぬるいヤマを掴ませるわけにもいかないんですよね。
どうなる!? 姫川玲子シリーズのこれから
――さて、シリーズではこのほど、『感染遊戯』が文庫化されました。こちらは物語内のサブキャラ3人を主役に据えたスピンオフ作品集です。企画の発端は?
誉田:勝俣を主役に1本書いてみようという構想は、実はけっこう前からあったんです。さらに、毎回犯人は捕まっているけど、本当の事件の背景がわからない……という短編集のアイデアを持ち込んだのがこの『感染遊戯』でした。
――今回メインに抜擢されたのは勝俣、倉田、葉山の3人。物語としての面白さもさることながら、ファンにとっては各キャラクターの知られざる一面などに触れられる、貴重な機会と言えそうです。
誉田:僕の立場からすると、この機会にあらためて設定を創り込んだわけではなくて、もともと存在しているものに“スポットをあてた”に過ぎません。これまで見えていなかったところが明らかになっただけで、彼らはずっとそういうかたちで存在していたんです。だからその意味では、機会さえあればみんなメインを張るだけのエピソードは持っていると思いますよ。
――今回、3人のキャラクターに共通するのは、ある種のダークサイドが描かれている点。葉山でさえも、内に抱える仄暗い部分に少しスポットがあたりました。俄然、今後の玲子や勝俣との絡みが楽しみです。
誉田:それは僕自身もぜひ見てみたいです。葉山は自身が抱えているものをどう処理し、周囲が彼をどう扱っていくのか。このあたりは本編含め、これからの展開を見守ってほしいですね。
――ファンとしてはほかにもこういうかたちでフィーチャーされることを期待するキャラは多いと思います。國奥先生などはファンの支持率も高そうですが。
誉田:実際、『感染遊戯』のなかで、國奥先生をやろうという案もあったんです。僕としても好きなキャラなんですけど、國奥先生というのは「これはこういう事件だ」と言うことはできても、解決能力を持っていないので物語になりにくいんですよね。まあ、またの機会にということで。
――さて、気になっているファンも多いと思いますが、姫川玲子シリーズの今後のスケジュールを教えてください。
誉田:2014年の後半に、『インデックス』という短編集が出ます。また、さらにその翌年になると思いますが、書き下ろし長編を1作出す予定です。
――ずばり、誉田さんの頭のなかでは、すでに相当先の展開まで構想が固まっているのでしょうか?
誉田:とりあえずはその書き下ろし長編まで、ですね。映画『ストロベリーナイト』をご覧になった方からすると、解体された姫川班の再結成こそが、望まれている展開だと思います。しかし現実的には、そう易々と再結成が叶うはずもなく、僕としてもそんな甘い展開を描くつもりはありません。そのあたりのさじ加減のようなものを、これ以降の作品で楽しみにしていただきたいですね。
――たしかに姫川班再結成は、目下、ファンにとって最大の期待でしょうね。
誉田:いまの時点では、どうなるのか僕の口からは何も言えません(笑)。ただ、予想通りの展開ではつまらないですからね。読者の皆さんの予想を裏切るような展開を、今後も続けていくつもりです。
――また、1人の女性としての玲子の行く末を心配するファンも多いようです。
誉田:そもそも、玲子が簡単に自分の幸せを掴めるような女性だったら、このシリーズがここまで続くことはなかったでしょう。それに玲子自身、いい旦那を見つけて寿退社して、ピンクのエプロンを身につけて家事をするような生活に幸せを感じるかというと、決してそうではないと思うんです。読者の皆さんだって、そんなの読みたくはないでしょう? だから、玲子にはもうひと頑張りしてもらわないと(笑)。
――最後に、再来年に予定される長編の構想を、言える範囲で教えてください。
誉田:まだ僕のなかにも漠然としたイメージしかないんですけど、玲子がこれまでになかったくらい、本気で“怒り”ます。まだプロットも何もない状態ですし、彼女がいったい何にそれほど怒っているのかは、僕にもわかりません。いわば、玲子が激怒しているシーンだけが予告編で流れているような状態です。実際にどのようなかたちに仕上がるのか、楽しみに待っていてください。
- 友清 哲 (ともきよ さとし)
- フリーライター兼、編集者。ビジネス誌や文芸誌などを主なワークフィールドとする傍ら、書籍の編集執筆に従事。著書は『作家になる技術』(扶桑社文庫)『R25 カラダの都市伝説』など多数。映画「ストロベリーナイト」オフィシャルブックや、『誉田哲也 All Works』(宝島文庫)の取材・構成なども手がけている。